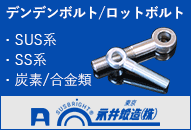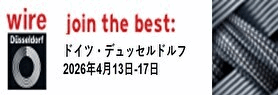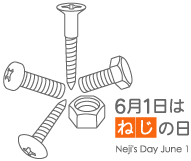「ねじの日特集号」を発行する。米国トランプ大統領が再任され、自国経済の再生を掲げて各国に対して高い関税を課す政策を推進している。この政策が示唆するのは、海外生産に依存してきた産業において、これらを米国内で生産するよう促すということだろう。
だが、企業側にとっては、関税分を加味しても依然として海外生産の方がコスト面で有利という現実がある。したがって、関税が上がったとしても、企業が海外生産をやめる理由にはならない可能性が高い。
製造業が衰退してきた原因の一つは、外国との競争力の低下にある。しかし、それ以上に深刻なのは、投資や金融といった高収益な分野に資本や人材が流れ、製造業が相対的に軽視されてきたという構造的な問題ではないか。自動車産業ですらその流れに抗えず、デトロイトの衰退はその象徴的な出来事である。
現在、アメリカの経営者や労働者が、自国経済のために、工場を構え、製品を作る覚悟を持っているかどうかは疑問が残る。製造業に代わる高収入の職種がある今、工場に人が集まらないのは無理もない。
日本もまた似た状況にある。最近の米不足は、長年にわたる減反政策や農業従事者の減少が主な要因であり、農業を「選ばれる職業」にするには、収入ややりがいといった実利が不可欠だ。旨味がなければ、人は動かないのだ。
もちろん、安価で供給する国からの輸入になるべく頼らず、自給を目指すというのは、採算を度外視したうえで、国家としても企業としても相当な覚悟が求められる。しかし、それを怠れば、主食の穀物や、ねじ・ばねといった機械要素部品ひとつまともに作れなくなってしまうという、由々しき事態を招きかねない。
「強い実体経済を取り戻せるか」という問いに真剣に向き合うならば、関税という短期的な手段だけでなく、なぜその産業が衰退したのか、なぜ人がそこに集まらないのか―根本的な構造に目を向け、政治制度や労働環境、教育、賃金制度まで含めた包括的な改革が必要だ。
もし外国との競争力の低下が原因であれば、関税を通じて一時的に防衛することは可能だろう。しかし、制度や社会的評価といった内的要因が産業の足かせになっているのであれば、その解決なくして産業の再生はあり得ない。
製造業が抱える「3K」(危険・きつい・汚い)のイメージを払拭し、働きやすさと誇りを感じられる職場環境を整えることも、強い実体経済を築くための不可欠な条件である。
産業の再生を本気で目指すなら、問われるのは覚悟と継続的な改革の意志だ。求められているのは、安易な保護主義ではなく、未来を見据えた地に足のついた国家戦略である。