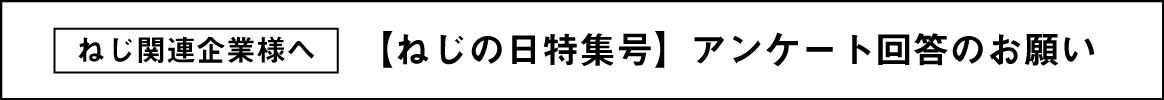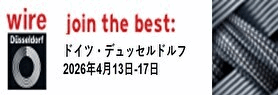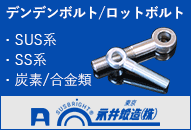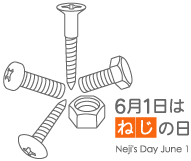ねじ産業と密接に関わるめっき業界は、共存共栄に向けた関係強化が求められている。ねじ業界にとってめっきは不可欠であり、両業界の協力がなければ高品質な製品の提供は難しい。全国鍍金工業組合連合会(全鍍連)の神谷篤会長(愛知県鍍金工業組合理事長)と山崎慎介副会長(神奈川県メッキ工業組合理事長)に、その取り組みを聞いた。
全鍍連は、全国23の工業組合から構成され、環境規制への対応や技能検定制度の運営、人材育成のための技術コンクール開催などめっき企業の地位の向上や経営基盤の強化を主な事業としている。2024年4月現在、所属企業1155社のうち283社がねじ用めっきを手がける。
環境規制の対応に向けて業界の実情に合わせた国への働きかけにも取組んでいる。一般排水基準が2006年に5㍉㌘/㍑から2㍉㌘/㍑に強化された亜鉛排水規制において、電気めっき業に適用される暫定排水基準(4㍉㌘/㍑)は昨年12月10日に適用期限を迎えていたが、2029年12月10日に延長された。未だ排水処理において直ちに解決が困難な課題があることから対応が難しいとされ、電気めっき業のみ暫定基準の延長が続いているが、めっき業界のコスト構造にも関係しているようだ。
環境規制の対応について、神谷会長は「中部圏の自動車関連向け事業者は、大ロットのバレル処理が中心で管理が比較的容易だが、小ロットを扱う都市部のねじ用めっき事業者は薬品や排水の管理負担が大きいだろう」と指摘する。亜鉛排水基準の厳格化に対しては、「延長ではなく暫定基準を正式な基準にしてほしい」との考えを示した。また、見直しされる土壌汚染対策法の地歴調査に関し、事業者の負担軽減のための税制優遇措置を求めている。※全鍍連は昨年12月に全国中小企業団体中央会にて、土壌汚染対策法の見直しにおける地歴調査について、事業者の費用負担の大きさやボーリング調査の物理的困難な問題点を意見に挙げている。
山崎副会長は「めっき業界はローテクからハイテクまで幅広いが、ハイテク分野では代替剤の導入やGX(グリーントランスフォーメーション)が進んでいる。排水規制は自動化や省力化に対応できる大手には対応可能だが、小規模事業者にとってはコスト転嫁が難しく、淘汰が進んでいる」と現状を語る。全鍍連では規制に対応できない事業者の支援を行っているが、「小規模事業者が消えれば、日本の産業基盤が弱体化する」と懸念を示す。
めっき業界は外部環境の影響を強く受ける。神谷会長は「かつては自動車のグリル向けにプラスチックめっき技術が進化したが、環境規制で需要が激減した。もし画期的な〝錆びない金属〟が開発されれば、業界が一気に縮小する可能性もある」と指摘し、「業界全体で連携し、情報収集を進め、〝日本めっき工業〟という一つの会社のように協力すべき」と提言する。
ファスナー業界との関係について、全鍍連は過去の調査で「付加価値が高く高い品質が求められる特殊品の処理が、規格品と同水準の単価で受注された事例」を指摘している。神谷会長は「めっき業界はモノを製造するのではなく、付加価値を付ける産業であり、どうしても上下関係が生まれて、取引先との関係でコスト競争を強いられる。例えば、装置の連続稼働を前提で単価設定をすると、停止が必要な際に採算が取れなくなる」とし、適正な受注価格の必要性を訴えた。
シアン化合物の供給問題では、国内唯一のメーカーが昨年末に生産を停止し、輸入依存が進んでいる。神谷会長は「シアンは我々にとっての欠かせないものであり、経済的事情で輸入がストップしてしまったら大変なことになる。資源のないものづくりに頼る国なのだから、国として生産継続の働きかけをすべきだった。サプライチェーンの脆弱性を改めて認識する契機となった」と語る。
環境規制への対応、適正受注価格の確保、サプライチェーンの安定化と、めっき業界は多くの課題に取り組んでいる。ねじ業界とめっき業界の共存共栄のためには、単独の事業者ごとの連携だけではなく、業界同士の協力体制の構築が不可欠だ。(取材=東京本社・大槻)